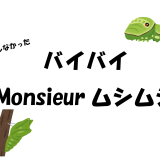こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
「終身雇用」
初めて聞いたときは「終身…死ぬまで?」って思った。
そんなはずはないとなんとなく思うようになったけど、厳密に「終身雇用」ってどういう意味なのかはよく分からない。
似たような言葉として「定年」っていうのがあるけど、それも厳密にはどういう意味なのかよく分からない。
どうやら、法律で決まっているわけじゃないらしいので、「定年」と「終身雇用」について整理してみる。

終身雇用とは、「定年まで解雇されずに働き続けられる」という企業慣行を指す言葉で、法的な定義はない。
実態としては「無期雇用契約」となる。
前回の記事(社員?バイト?パート?違いってなに?)で、社員・バイト・パートといった分類を、「雇用形態」「雇用期間」「労働時間」の3軸で整理した。
そのうちの「雇用期間(無期雇用/有期雇用)」が無期雇用にあたるのが「終身雇用」ということになる。
つまり、
- 終身雇用とは無期雇用のこと
- 解雇されない保証ではないが、企業が長期雇用を前提として人材を雇う制度・慣行
という感じ。
特に戦後の高度経済成長期の日本では、この慣行が広く普及した。
「終身雇用」といっても、法的には「終身雇用制度」は存在しないし、企業は経営状況に応じて人員整理をすることもできる。

「定年まで解雇されずに働き続けられる」という中で、定年とはどういう意味なのか。
厚生労働省によると、
定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度をいいます。
モデル就業規則【第51条 定年等】1
こんな感じらしい。
定年制度は、企業が労働者に一律の年齢で区切りをつけるための企業内独自の制度で、「就業規則」に絶対的必要記載事項として必ず記載しなければならない(労働基準法第89条)。
定年制度自体は法律で義務付けられているわけではないが、一定規模以上の企業では就業規則の作成義務があり、法律との関係もある。
労働者が常時10人未満の事業場には、就業規則の作成義務がないため、定年制度を規定していないこともある。
定年制度を規定する際、60歳未満は法律で禁止されているが、上限は法律で明確に定められていないため、企業が70歳以上に定年年齢を設定することも可能となる。

「定年」という言葉は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」の中で出てくる。
高年齢者雇用安定法は、高齢になっても安心して働き続けられる環境を整えるという目的で、以下のようなルールが設けられている。
1.60歳以上の定年(第8条)
企業が定年制を設ける場合、60歳未満にすることは禁止されている。
ただし、坑内作業のように高年齢者が従事するのが困難な業務については例外が認められる。
2.65歳までの雇用確保措置(第9条)
定年を65歳未満に設定している企業は、以下のいずれかの「高年齢者雇用確保措置」をとる義務がある。(定年の65歳への引上げを義務付けるものではない)
- 定年制の廃止
- 65歳までの定年の引き上げ
- 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入
継続雇用制度は、定年後も希望すれば再雇用などで働き続けられる制度のことで、関連会社(特殊関係事業主)での雇用継続を含めることができる。
3.70歳までの就業機会確保(第10条の2)
2021年(令和3年)からは、70歳までの就業機会確保措置が努力義務として以下のように定められている。(定年の70歳への引上げを義務付けるものではない)
- 70歳までの定年引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳以上までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
労働者それぞれの事情に配慮しながら、70歳まで働ける道を複数用意し、企業にそのいずれかを制度化するよう求めている。

定年は、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする制度。
なので、労働者ではない公務員には定年制度はないのかという疑問がわく。
どうやら公務員は、国家公務員法・地方公務員法という法律に定年が明記されているみたい。
- 国家公務員:令和5年度以降、段階的に定年を60歳から65歳へ引き上げ中(国家公務員法第81条の6第2項)
- 地方公務員:国家公務員の定年を基準にして条例で定める(地方公務員法第28条の6第2項)
国家公務員も地方公務員も、定年を60歳から65歳へ引き上げている途中らしい。
この動きは、公的年金の支給開始年齢が、平成25年度以降段階的に60歳から65歳へ引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないように雇用と年金の接続を図ることが背景となっている。
こんな感じに、公務員にも定年制度はあるが、その定年年齢や扱いが法律で直接規定されている点が、就業規則に基づく民間企業の定年制度とは異なる。
一方で、準公務員(独立行政法人職員など)はそれぞれの組織の就業規則に定年が定められており、公務員の定年延長の動きに合わせて、同様に定年が延長される傾向にある。

終身雇用とは、「無期雇用」を前提とした企業慣行で、法的な制度ではなかった。
定年とは、労働者が一定の年齢に達したことを退職の理由とする、就業規則で必ず定める必要がある制度。
高年齢者雇用安定法によって、60歳未満の定年は禁止され、65歳・70歳までの雇用確保措置が企業に求められている。
公務員にも定年制度はあるが、その定年年齢や扱いが法律で直接規定されている点が、就業規則に基づく民間企業の定年制度とは異なる。
少子高齢化、物価上昇、財政難と経済社会の課題によってその時代の働き方も変わってきているみたい。
 僕のYeah!
僕のYeah!