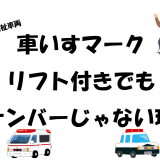こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
「原付がなくなる」
「免許が増える」
そんな噂を最近耳にした。
いや、目にした…?
原付がなくなるの?
新しい免許が新設されるの?
そう思って少し調べてみたら、「新基準原付」なるものが追加されて原動機付自転車(いわゆる原付)の制度が進化するというお話っぽかった。

とりあえず、原付(第一種原動機付自転車)というのは、
・排気量50cc以下(または定格出力0.6kW以下)の二輪車
・最高速度30km/h制限
・二段階右折が必要
・原付免許や普通自動車免許で運転可能
こんな感じの特徴を持つ小型バイク。
この小型バイクを取り巻く状況に大きな変化が起きてきたみたい。

制度見直しのきっかけは、2025年(令和7年)11月以降に適用される新たな排ガス規制。
これは、欧州連合(EU)が定めた排出ガス基準「Euro 5(ユーロ5)」と同程度の内容で、より厳しい環境基準に適合する必要がある。
- Euro 5とは、EUが自動車の排気ガスに対して設定した5回目の基準のこと
- 日本でもこれと同等の排出ガス規制が、総排気量50cc以下で設計最高速度が50km/hを超える原付に適用される
この規制強化で、以下のような課題が明らかになった。
- この新基準をクリアする車両を開発するのは困難で、開発コストも高騰
- 採算が取れないため、従来の50cc原付の生産・販売の継続が難しくなる
つまり、今のままでは小型バイクである「原付」というカテゴリが市場から消えてしまう可能性があった。
そこで、技術的・制度的な対応として、「総排気量125cc以下で、最高出力を4kW以下に抑えたバイク」を“原付的な存在”として位置づけ直す動きが出てきた。
有識者検討会で、
- 技能試験官による走行評価
- 一般運転者(原付未経験者含む)の試乗会
などなどを通じて、こうした新基準車両が現行原付とほぼ同等の運転特性を持つことが確認された。
その結果、
- 道路運送車両法上の第一種原動機付自転車の区分や外見識別、出力制御などの制度整備を進めること
- 道路交通法上の一般原動機付自転車の区分より、新基準原付を原付免許で運転可能とすること
といった方向性が定まった。
※参照元:「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会 報告書概要(PDF)」

道路運送車両法上の「道路運送車両」は「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」に分けられ、原動機付自転車は更に「第一種原動機付自転車」「第二種原動機付自転車」に分けられる。
制度見直しによって追加されたのは、「第一種原動機付自転車」の「最高出力4.0kW以下かつ総排気量125cc以下の二輪」という箇所。
この追加項目が新基準原付。
排気量[L][cc]とは、エンジンが1度に吸い込める空気と燃料の容積。
定格出力[kW]とは、安定して出力し続けられる電力。
最高出力[kW]とは、エンジンが発生する最高の出力(最大馬力[PS])。

道路交通法上の「車両」は「自動車」「原動機付自転車」「軽車両」「トロリーバス」に分けられ、原動機付自転車は更に「一般原動機付自転車」「特定小型原動機付自転車」に分けられる。
こちらの法律も、制度見直しによって「一般原動機付自転車」の「最高出力4.0kW以下かつ総排気量125cc以下の二輪」という箇所が追加された。
新基準原付の構造の追加項目に伴って、免許における区分にも同じように追加された。

なので、今回の見直しで原付免許そのものがなくなるわけでもなく、今まで乗っていた原付が乗れなくなるというわけでもない。
つまり、原付免許で「新基準原付」というものも運転できるようになったということ。
新基準の区分について以下のような埼玉県警察のwebページにも案内があった。


結局、制度的には原付がなくなるわけでもなく、免許が増えるわけでもなかった。
でも実態としては、規制強化によって総排気量50cc以下の原付一種の生産が終了するっぽい。
原付きバイクの国内での生産は現在、ホンダとスズキのみが行っていて、排ガス規制の強化に伴い、終了する見通しとなりました。
原付きバイク ホンダとスズキ 生産終了を検討 国内生産終了へ
生産終了とはなるが、制度がより現代の技術や交通事情に合うようにアップデートされるというのが正しい理解かも。
ちなみに、最近話題の「特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)」とは今回の見直しとは別の制度。
 僕のYeah!
僕のYeah!