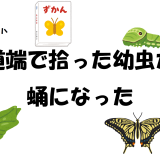こんにちはこんばんはいらっしゃいませおはようございます。僕です。
暑い日に
「今日も真夏日だなぁ~」
と思ったり、実際に会話したりする。
気温によって暑い日の呼び方が変わったような気がするけど、正確には覚えてなかった。
ので、調べてみた。

気象庁の定義では
・夏日(なつび)
最高気温が 25℃以上の日。
・真夏日(まなつび)
最高気温が 30℃以上の日。
・猛暑日(もうしょび)
最高気温が 35℃以上の日。
・熱帯夜(ねったいや)
夕方から翌朝までの最低気温が25℃以上の夜。
こんな感じに定義されていた。
どれも気温を基準とした呼び方で、気温が上がるほど名前も強そうになっている。
また、寒い日の分類もあるみたいで、
・冬日(ふゆび)
最低気温が0℃未満の日。
・真冬日(まふゆび)
最高気温が0℃未満の日。
こんな感じに定義されていた。
つまり、気象用語では「○○日」という言い方で、気温帯に応じた表現をしていることがわかる。
また、最近登場している「酷暑日」「超熱帯夜」という言葉は、気象庁が定めたものではない。
これは、一般財団法人日本気象協会というところが、2022年に独自に提案した言葉で、極端な暑さに対する注意喚起のための目安として使われている。
・酷暑日(こくしょび)
最高気温が40℃以上の日。
→ 猛暑日(35℃以上)をさらに超える極端な暑さ。
・超熱帯夜(ちょうねったいや)
最低気温が30℃以上 の夜。
→ 従来の熱帯夜(25℃以上)よりも厳しい暑さが夜通し続く状態。
これらは公式用語ではないけど、ここ数年の気候変動や熱波の影響もあり、「35℃や25℃を超えても、もはや異常とは言えない」という現実を反映したものともいえそう。

ひとくちに「○○時の気温」と言っても、それはその時点の瞬間の気温ではない。
気象庁の定義では、「○○時の気温」とは「○○時の前1分間の平均気温」のこと。
たとえば、「12時の気温」とされている数値は、11時59分〜12時00分の1分間の平均気温となる。
また、最高気温や最低気温の観測時間帯についても注意が必要。
新聞などでは、最高気温は15時まで、最低気温は9時までに観測されたものが掲載されることが多く、1日を通じた気象庁発表のデータとは異なる場合がある。
たとえば、夜間に最高気温が記録されるような特殊な気象条件があれば、新聞と気象庁で「今日の最高気温」がずれることがある。

局地的な異常高温の原因となる現象として「フェーン現象」がある。
フェーン現象は、湿った空気が山を越えて風下側に吹き下ろす際、乾燥した熱風となって気温を上昇させる現象のこと。
- 山を登るとき:湿った空気が水蒸気を放出しつつ100mで0.5℃気温が下がる
- 山を下りるとき:乾燥空気が圧縮されて100mで1.0℃気温が上がる
このフェーン現象によって、夏の暑さに拍車がかかる。
実際に1933年7月には、山形市で 40.8℃ という当時の国内最高気温が記録されており、これはフェーン現象の影響だとされている。

気温によって呼び方が変わる暑さの分類は、知っていると意外と便利。
「今日は猛暑日になるらしい」と聞けば、それは最高気温35℃以上の過酷な暑さを意味しているし、夜も25℃を下回らなければ「熱帯夜」となる。
特に夏場は、熱中症や冷房の使い方を考えるうえでも、こうした指標が生活の判断材料になる。
予報士の口から出る「真夏日」や「猛暑日」という言葉が、ただのあいまいな表現ではなく、きちんと基準のある定義だということがわかるだけでも、日々の天気の見え方が少し変わってくる。
名前を知っておくと天気予報がちょっと楽しくなる。
 僕のYeah!
僕のYeah!